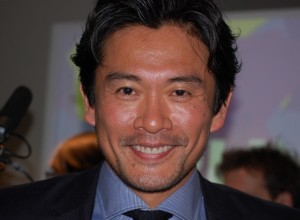第64回ベルリン国際映画祭(2) - 山田洋次監督の反戦への想い
今年のベルリン映画祭のコンペ部門は、華やかな「グランド・ブダペスト・ホテル」で開幕し、山田洋次監督の「小さいおうち」で幕を閉じた。山田洋次監督はベルリン映画祭のいわば常連だが、今回の映画はこれまでの山田作品とはひと味違うとベルリンでは受け取られたようだ。この映画に出演した黒木華(はる)さんが銀熊賞の最優秀女優賞を受賞したが、ドイツの新聞批評のなかには「山田監督のおかげで受賞できたのだろう」と辛口のものもあった。山田監督は黒木華に「特別の演技はしなくていい」と注文を付けたとか、彼女の演技らしくない演技、彼女の持ち味と自然な立ち居振る舞いが審査員に評価されたのかもしれない。
「小さいおうち」は、亡くなった大叔母が残した自叙伝を読む青年の現代と、大叔母が東京の赤い屋根のおうちで女中として働いた時代の間を行ったり来たりしながら、進む人間ドラマである。日中戦争が始まった頃の時代を背景に、その家の夫人と夫の同僚で芸術家肌の若い男性との密やかな恋に若き日の大叔母(黒木華)の想いも絡むという重層的な映画だ。詩的で美しい画面の背景に大きなドラマが隠されている。原作は中島京子の直木賞受賞作の同名の小説で、山田監督はこの小説を本屋で見つけ、買って帰って読んだ後ぜひ映画化したいと作者に手紙を書いたという。映画化する段階で原作者と山田監督の間で突っ込んだ話し合いが行われたということだが、山田監督は「この小説には僕の少年時代の東京が描かれていて、僕自身の物語のような気がした。当時を知らない若い人が戦争中のことを書くと必ずどこか違和感を持つのだが、この作品にはそれがない。中島氏がこの時代のことを徹底的に調べて書いたためだと思う」とベルリンでの上映後の記者会見で語っていた。
この映画に対しては「反戦映画としては甘く、物足りない」といった批判が聞かれた反面、「現代の青年の疑問に答える形で当時の日本の雰囲気がよく伝えられていた」「ほのぼのとした家族をテーマにしてきた山田監督のこれまでの作品とはひと味違う良い映画だった」という声も聞かれた。この受け取り方の相違は、映画のなかの至る所に示されている山田監督なりの反戦の思想を、見る側がどれだけ重く受け取るかによって違ってくるという気がする。決して声高な主張ではないけれど、子どもとして戦争を経験した私は、それをはっきり感じ取った。そして記者会見でそれが間違っていなかったことを知ったのだ。
山田監督は「戦争が個人の生活にどういう影響を与えるかを描きたかった。これは、1935年ぐらいから1945年くらいまでの戦争中の話で、当時は妻が夫以外の男性を好きになることを罰する刑法が存在していた。日本の戦争中のことを知っている人は少なくなり、僕はその最後の世代。その経験を今の観客に伝えたいと思った」と戦争を知る世代の使命感も明らかにした。「現代の日本では戦争を知っている世代と知らない世代の間に大きなギャップがある。総理大臣をはじめ日本の指導者は戦後に生まれている。残酷で悲劇的な戦争を2度と起こしてはいけないという教訓をしっかり学んで生きているのだろうかと心配でならない」と危機感も表していた。
旧満州の大連生まれで、その大連で中学1年の時に敗戦を迎え、日本に引き揚げてきたという山田監督自身の自叙伝を映画化して欲しいという気持ちが記者会見の間に生まれ、私は会見後の山田監督にその希望を伝えてしまった。実現してくださることを切望する。
ベテランの監督だけでなく新進気鋭の日本の作家たちの活躍も今年は目立った。ジェネレーションKプラス部門で特別表彰を受けた「人の望みの喜びよ」(震災で両親を失った少女と幼い弟の物語)は、杉田真一監督の初めての長編映画である。また、フォーラム部門で映画祭の本賞とは別の独立の国際批評家連盟賞を受賞した「FORMA」(二人の若い女性の心理的葛藤を描いた作品)の坂本あゆみ監督も、これがデビュー作である。「FORMA」は、審査員から「シンプルな作りでありながら、人間の微妙な感情を表現している。未来を感じる作品」と評価されたという。さらにパノラマ部門の「家路」の久保田直監督も劇映画のデビュー作品でベルリン映画祭に招かれた。福島第一原発の事故による放射能汚染で避難を余儀なくされた村人たちのふるさとへの想い、代々自分の土地で農業を営んできた人たちの農作業への郷愁を取り上げた作品だ。時に涙しながら見終わったが、解決策のない現実に対する絶望感は重く残った。ベルリンの観客には、放射能に汚染された危険なふるさとに若者が母親と戻って農業を続けるという心理がよく理解できなかったようである。
この映画を見終わったあとの取材で「放射能による被害を受けて避難せざるを得なくなった村人をテーマに取り上げながら、はっきり脱原発の姿勢を示していないのはなぜか?」と聞いたところ、久保田監督からは「そういうことをはっきり言うと偏ったものと受け取られ、多くの人に見てもらえない」という答えが返ってきた。ベルリンの観客がこの映画に戸惑いを見せたのは、その辺の意識の違いのためではなかっただろうか。ドイツ人観客には、はっきりと脱原発の主張を貫いた映画の方が受けたのではないかと思われる。ちなみに「撮影は、一日の滞在時間が規制されている放射能汚染地域で福島オールロケでおこなった」と同監督が答えたのも驚きだった。放射能の危険に対する危機感が薄いのが気になった。
震災の被害を取り上げた日本映画はもう1本あった。ジェネレーション14プラス部門に参加した平林勇監督の短編映画「SOLITON」である。この映画は14分の短いものだが、最初観客が見せられるのは、ただひたすら歩き続ける人の運動靴だけ。最後の方になってその運動靴が到達するのが、津波の被害を受けた土地だと分かる。運動靴は津波による漂流物の間を歩き続けるのだ。平林監督は、2012年のベルリン国際映画祭・同部門に出品した短編アニメ映画「663114」で、特別表彰された作家である。暗号のようなタイトルは、戦後66年の3月11日に起こった4基の原子炉の事故を意味しており、8分の短編で事故後の未来を描いたことが評価されたのだった。残念ながら今年は賞にはいたらなかった。
。